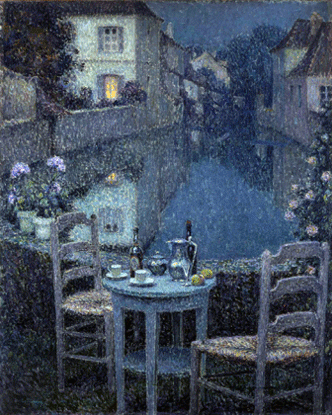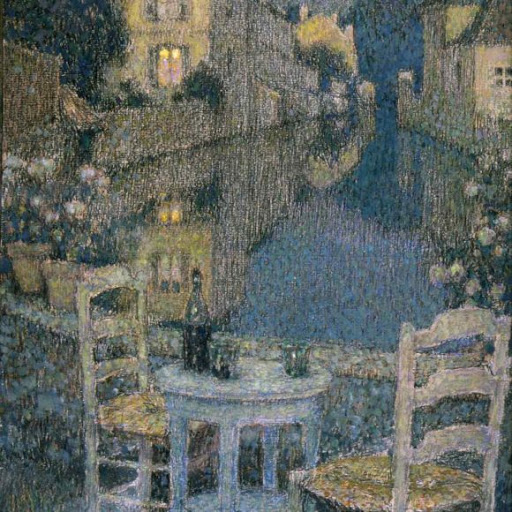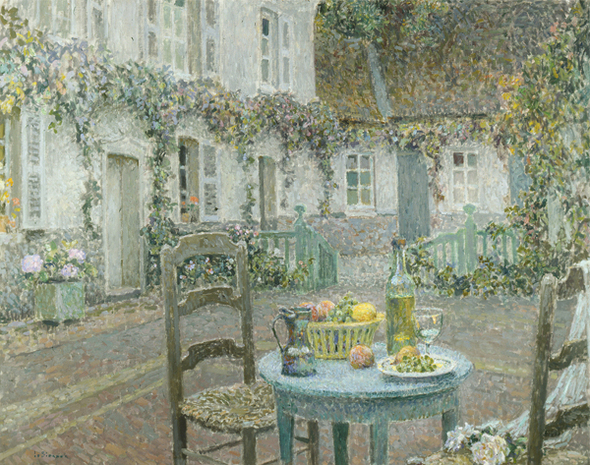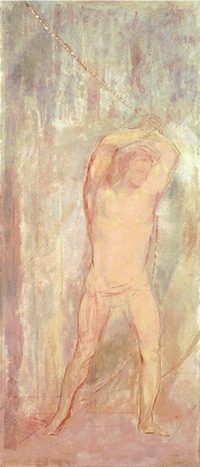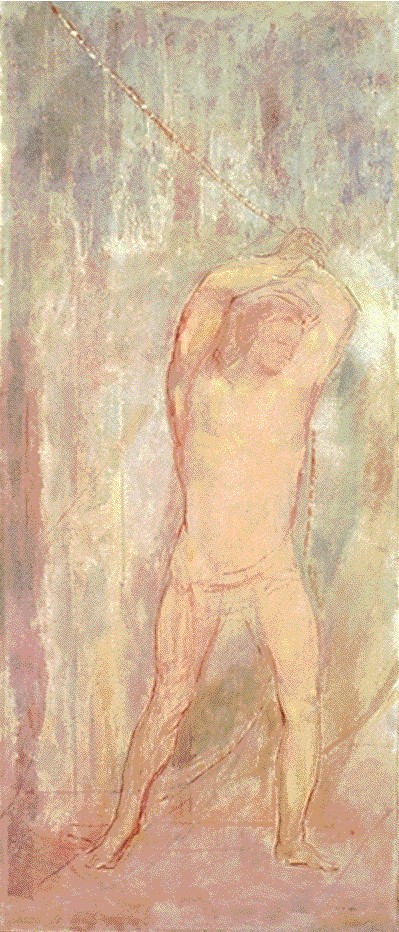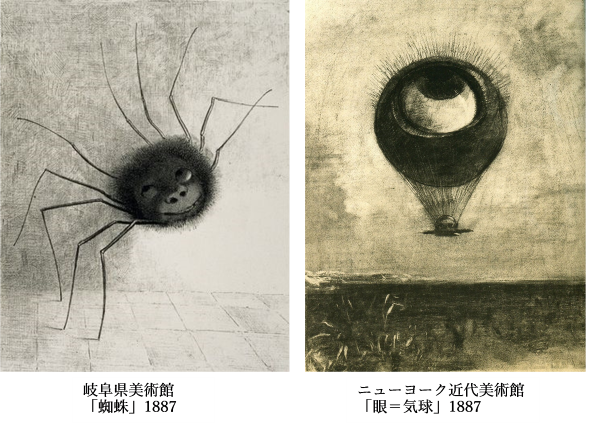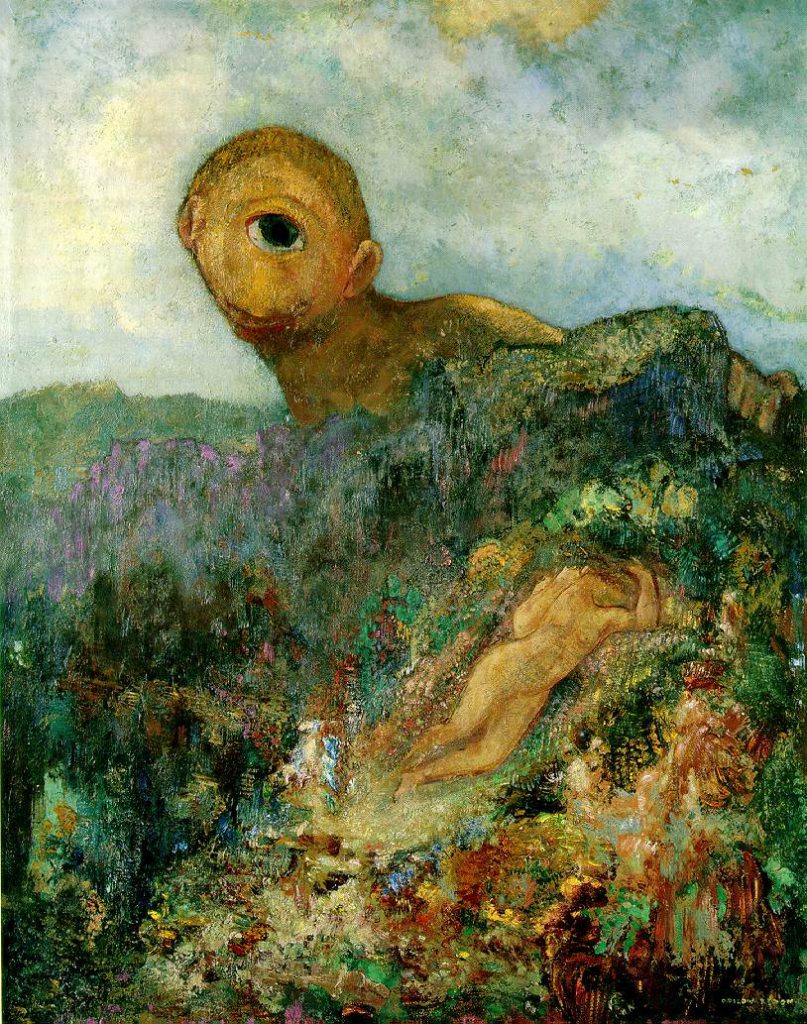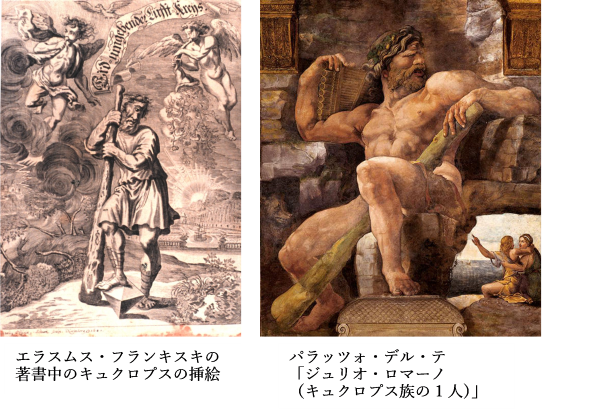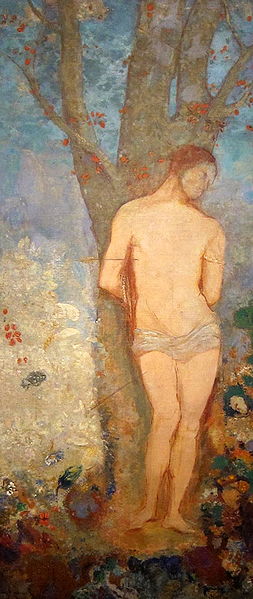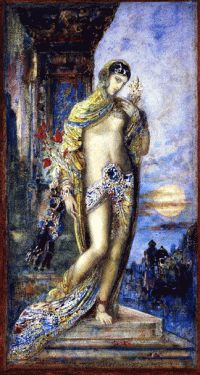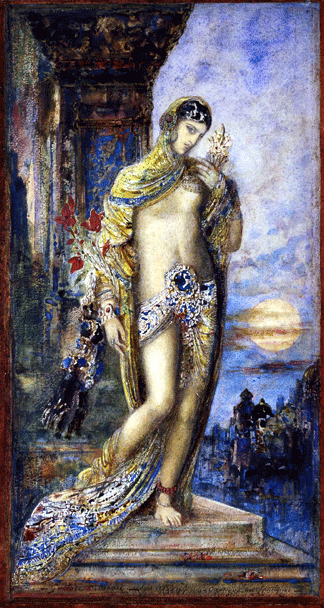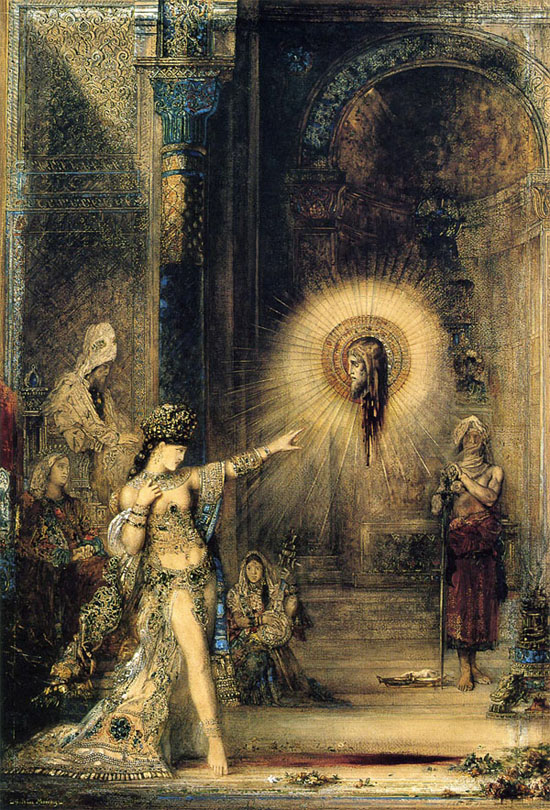美観地区(倉敷川)のほぼ中央に架かる橋です。

【鑑賞の小ネタ】
・コンクリートではなく石橋
・太鼓状に湾曲
・橋桁はなんと一枚岩
・橋柱に刻字された文字に注目
・川舟に乗らないと見られない文字あり
倉敷川の最上流に「今橋」が架かっていて、川を下って次に現れるのが「中橋」です。約10mの川幅に架けられている橋で、明治10年(1877年)に、れまで木造だった橋を石橋に架け替えたそうです。橋桁 (欄干の下の部分) は花崗岩の一枚岩で、太鼓状に湾曲しています。そして、桁の長さは、全国の石桁橋の中で最長なんだそうです。


橋柱に文字が刻字されています。

当時の倉敷村会議員だった原唯七によって漢字と変体仮名で刻字されたそうです。この「槗 」という漢字は「橋」の異体字で、変体仮名(なかはし)の元の漢字は「奈可者之」のようです。これはなかなか読めませんよね。
中橋のたもとは、人力車の乗り場にもなっています。

主な乗り場は倉敷物語館前なのですが、中橋のたもとでも乗り降りできます。営業時間は、9;30~日没までとなっています。
中橋の内側に、橋が作られた年と作った人の名前が刻み込まれているのですが、川舟に乗らないと見えません。筆者は川舟に乗って中橋の下をくぐったことがあるのですが、夕暮れ時だったため、はっきりと確認することができませんでした。刻字に興味のある方は、天気の良いお昼間をお勧めします。
《くらしき川舟流し》の川舟乗船場は中橋を少し下ったところにあります。
ところで、中橋は壊れたことがあるようですよ。自動車が渡ったからみたいです。石橋でも壊れるんですね。中橋を渡ると分かるのですが、段があるんです。そして、短い石柱が橋の両側に2本ずつ立っています。これは、自動車の侵入を防ぐためだったようです。

向こう端(写真奥)の方が、段差が少し大きいように思います。こちらです。

何でこんな所に不自然な段差と石柱が?とよく思っていましたが、自動車侵入による破損の歴史があったんですね。