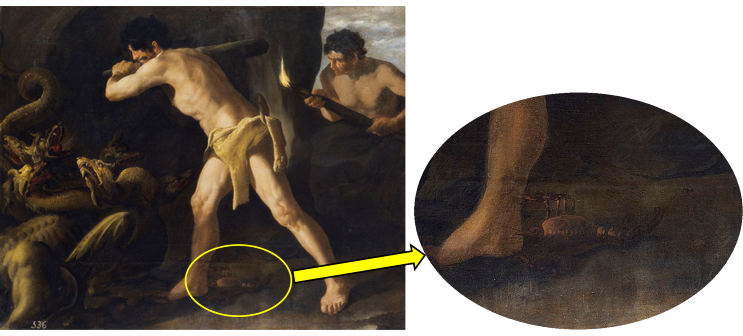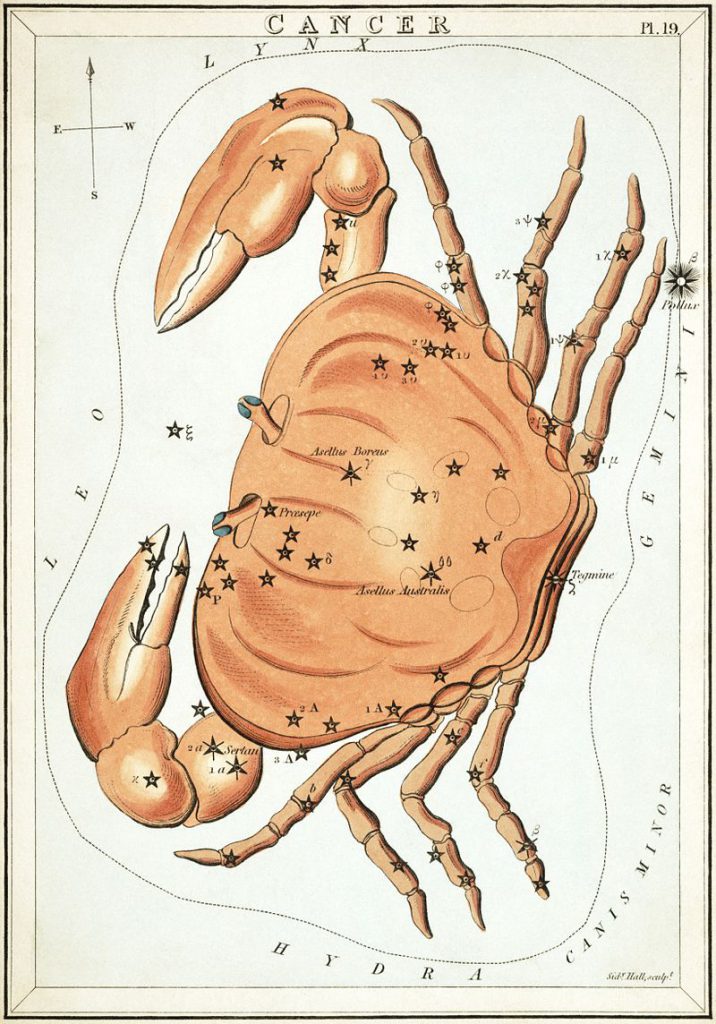美しい田園風景ですね。
 大原美術館
大原美術館
ジャン=バティスト=カミーユ・コロー(1796-1875)
『ラ・フェルテ=ミロンの風景』1855-1865
【鑑賞の小ネタ】
・コローはバルビゾン派の中心人物の1人
・風景画を多く描いている
・60歳過ぎてからの傑作多数
・中央の建物に注目
パステル画のような色合いの油彩画だなと思いました。ミレーと同じく、バルビゾン派の画家の1人とされています。中央の角ばった大きめの建物、何だと思いますか?中世のお城かなと思ったのですが、お城にしてはどうも中途半端な造りなんです。遠近法的には、かなり遠くに見えていますよね。そうだとすると、結構大きな建物ということになります。やはり、お城でしょうか…?
お城でした。
 出展:Wikipedia
出展:Wikipedia
Chateau La Ferte-Milon (シャトーラフェルテミロン)
未完成の城の廃墟なんだそうです。中途半端な造りはそのためでした。このお城、歴史は古いそうです。9世紀には存在していたようですよ。11世紀初頭、城の礼拝堂は大学になっていたという記述がありました。1394年、オルレアン公ルイドルレアン(ルイ・ド・ヴァロワ)は、既存の建造物を破壊して再開発を行っています。ところが、1407年にオルレアン公が暗殺されて、9年後に城の建設は止まってしまいます。そして、1594年にアンリ4世により解体されたということです。
 出展:WIKIMEDIA COMMONS
出展:WIKIMEDIA COMMONS
Chateau La Ferte-Milon (シャトーラフェルテミロン)
お城の内側の写真ですが、なんかすごいですね。よく現在まで残ったと思います。コローの時代でもしっかり廃墟感は出ていたと思いますが、そんなことは関係なく、ずっとこの辺りのランドマークであり続けているのだと思います。
大砲がありますよね。第一次世界大戦前のロシア製の大砲らしいです。「M1909 152㎜榴弾砲」というフランスのシュナイダー社設計(ロシア帝国が発注)の大砲が存在するようなのですが、何か関係があるのでしょうか?
 出展:WIKIMEDIA COMMONS
出展:WIKIMEDIA COMMONS
シャトーラフェルテミロン
19世紀頃の古いポストカード
お城の左側に、お城ほどではありませんが、背の高い長方形の建物が見えます。上部が平らではなくいくつか突起があって特徴的です。この建物は何でしょうか?
 出展:Wikipedia
出展:Wikipedia
Eglise Notre Dame(ノートルダム教会)
この教会だと思います。地図を見るとお城の近くにありました! カトリックの教会です。建物の上部の形状もコローの絵とよく似てますよね。先のとがった尖塔で飾られています。余談ですが、「ノートルダム」とは、フランス語で「我らの貴婦人」という意味で、聖母マリアのことを意味します。聖母マリアを信仰の対象としているということなので、カトリック系の教会というわけです。
絵の一番手前に、大きく農民の女性が描かれています。右奥には、農作業をする農夫と牛がいますね。「農民画家」ミレーと同じく、コローも風景の中に農民(一般の人々)をよく描き込んでいます。
コローが凄いのは、60歳過ぎてから多くの傑作作品を残しているところだと思います。大器晩成型だったわけです。恵まれた環境に育ったコローは、生涯金銭面で不自由することはありませんでした。友人や後輩を援助したり、パリの貧しい人々に寄付をしたりもしています。人柄も穏やかだったようですョ。じっくり画業に取り組めた人生だったことがうかがえます。作風に表れてますよね。特に大原美術館のこの作品は、ガツガツしてなくて、ほのぼのとした印象を受けます。
次の作品も、コローの特徴がよく表れていると思います。同じ頃に描かれています。
 ボルトン美術館
ボルトン美術館
ジャン=バティスト=カミーユ・コロー
『ボーヴェ近郊の朝』1855-1865
ちなみに、コローの弟子にカミーユ・ピサロがいます。
 グラスゴー美術館
グラスゴー美術館
カミーユ・ピサロ(1830-1903)
『曳船道(マヌル河の岸辺、荷を運ぶ小道)』1864
コローの影響を受けているのがよく分かる作品だと思います。ピサロはその後、印象派の中心的存在になっていきます。コローとピサロに限らず、画家同士の関わりを調べると、作風にその影響が見られて、なかなか興味深いですョ。