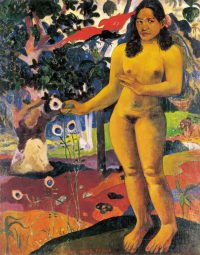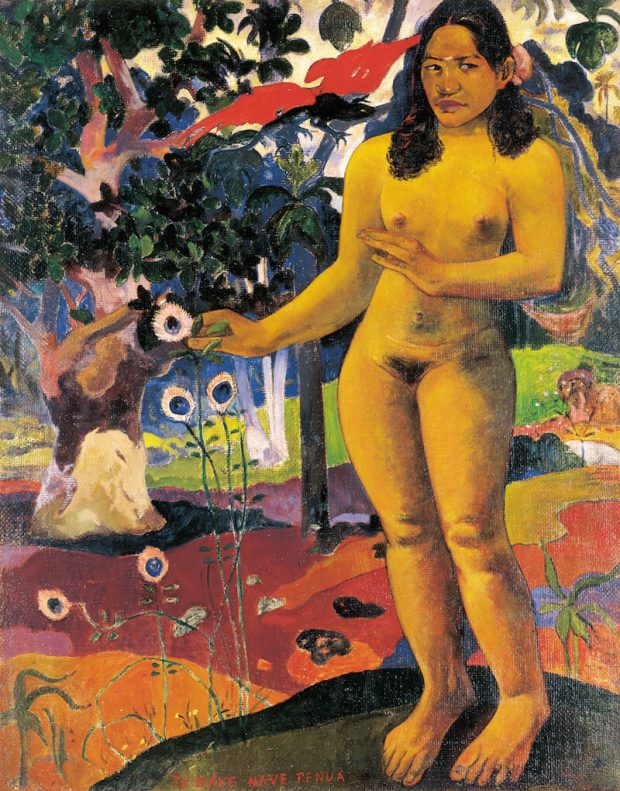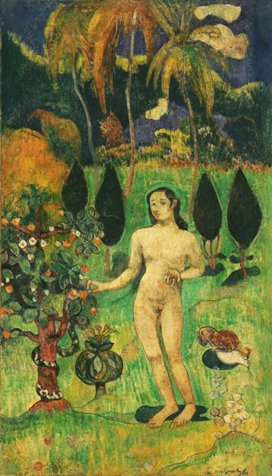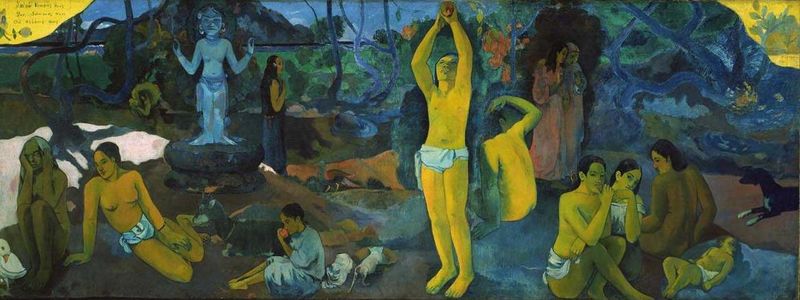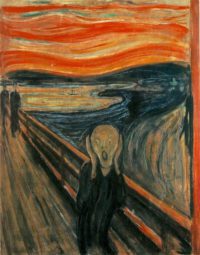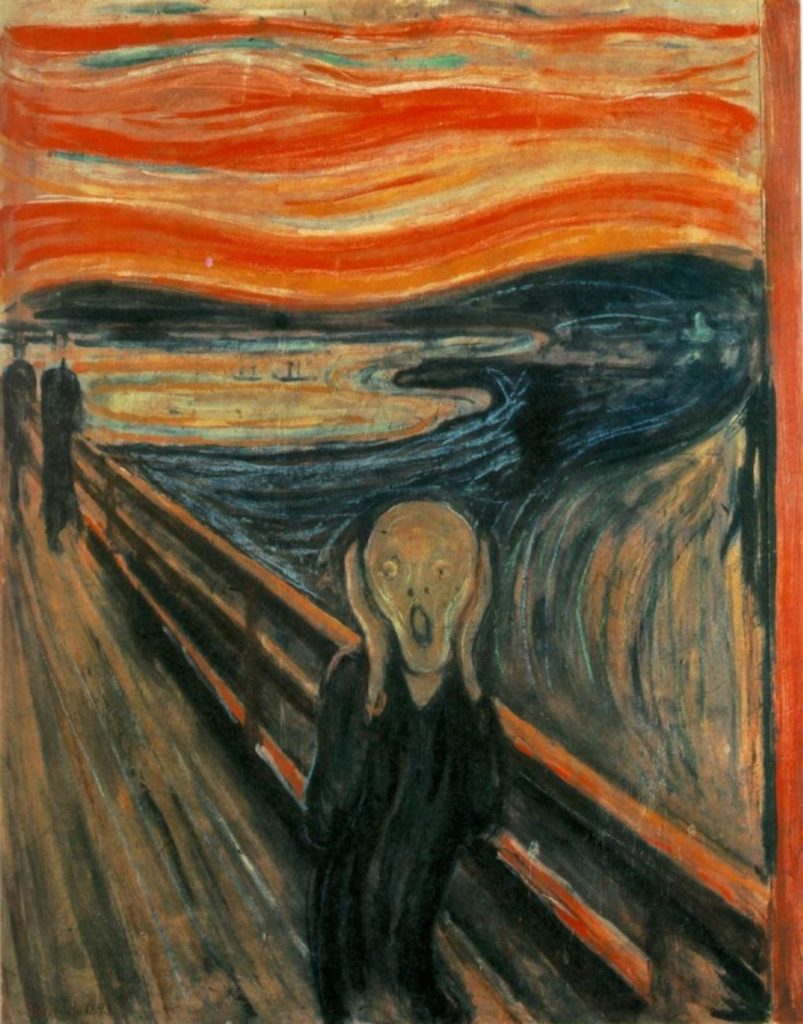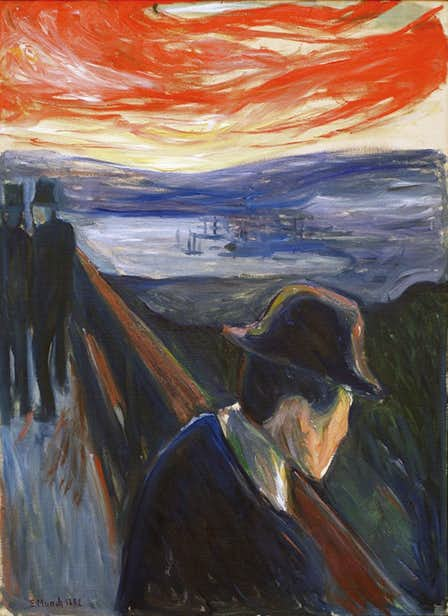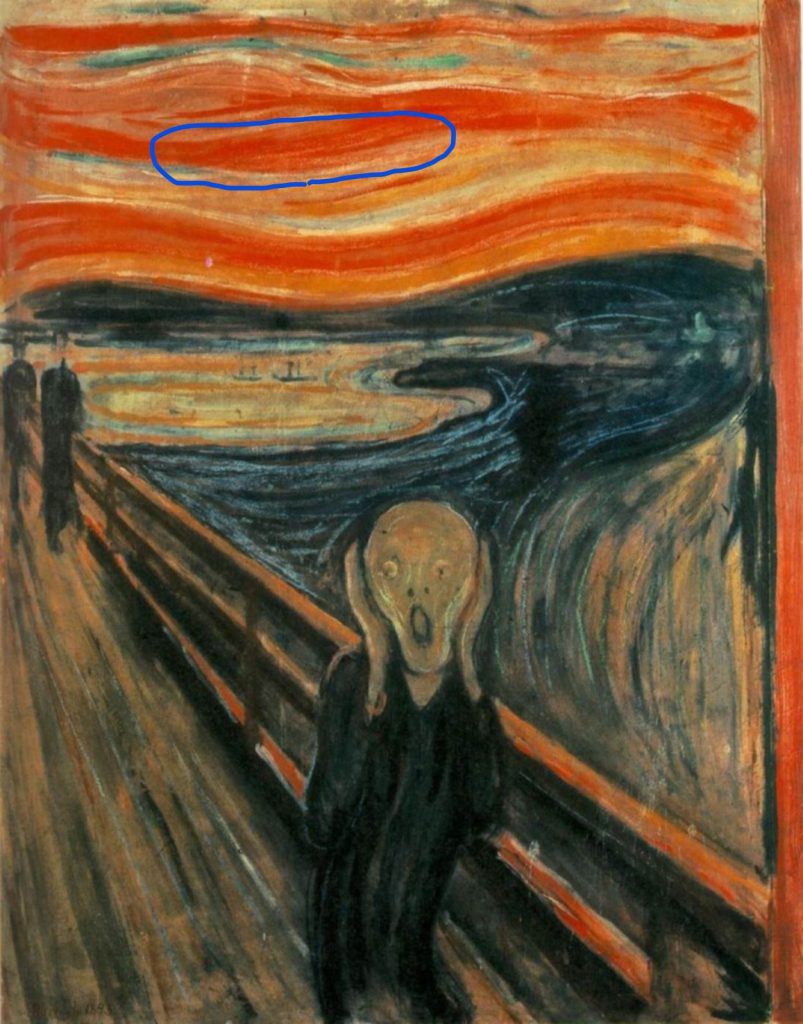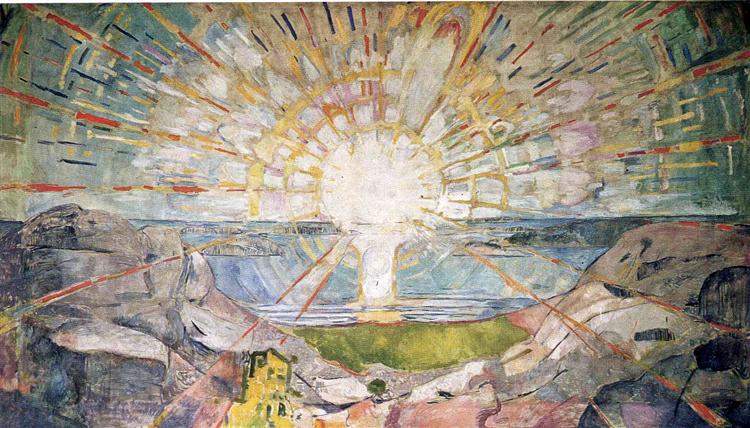美観地区内の倉敷川は、定期的に清掃が行われる等、とても管理されているようです。清掃の際に、どんな魚がすんでいるか、生き物調査も行われています。オオクチバス(ブラックバス)やブルーギル等の外来種がほとんど見られないらしく、主に在来種がすんでいるとのことで、ほんとに素晴らしいと思います。

ニゴイ、カワムツ、カマツカ、オイカワ、ギンブナ、ヤリタナゴ、アブラボテ、メダカ、ヨシノボリ、コウライモロコ、メナダ、アユなどです。メナダはボラの仲間で河川汽水域に生息します。汽水というと、海水と淡水が混ざり合っている水のことなので、あれ?と思いました。倉敷川はそもそも海と繋がる運河だったので、その名残りなのか?と期待してしまいましたが、これは多分、倉敷川の水源が地下で高梁川(岡山の三大河川の1つ)の下流と繋がっているからだと思います。アユについては、高梁川では毎年、稚魚の放流が行われているので、倉敷川にいてもおかしくないということなんだと思います。外来種の魚がほとんどいないおかげで、稚魚が捕食されることもなく生き残れていることに感動します。
久しぶりに美観地区に行ってみました。倉敷川を見ていたら、いました!

まあまあのサイズのスッポンです。多分キョクトウスッポンだと思います。現在のスッポンの生息状況は、大昔から日本にいるスッポンと近年改めて中国他から来た外来種のスッポンが混在している状態なんだそうです。
スッポンはすぐに川の中へ消えて行きました。ちなみによく見かけるアカミミガメ(ミドリガメ)は外来種ですね。
この鳥もよく倉敷川を訪れています。

アオサギです。よく飛んで来ています。美観地区のアオサギは、かなり近くまで寄っても逃げません。この時は川魚を狙っているようでした。

そしてそして、倉敷川の水源近くには白鳥がいます。

普段はオスとメスの2羽なのですが、ヒナがいる時もあって、とてもかわいいです。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、この写真のヒナは親鳥と同じポーズを取っているんですョ。上手に毛づくろいです。
白鳥にも色々種類があって、この白鳥は、くちばしがオレンジ色でくちばしの上部の付け根あたりに黒いコブがあるので、コブハクチョウだと思います。本来は日本にいない外来種の白鳥なんだそうです。
倉敷川(美観地区)の白鳥は大事に飼育されているようです。エサを鳩(土鳩)に横取りされているのをよく見かけます。鳩が調子に乗り過ぎると、威嚇していますが、基本的には見て見ぬふりをして平和に過ごしているように見えます。ほのぼのとした美観地区の癒しスポットだと筆者は思っています。


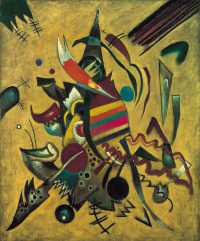
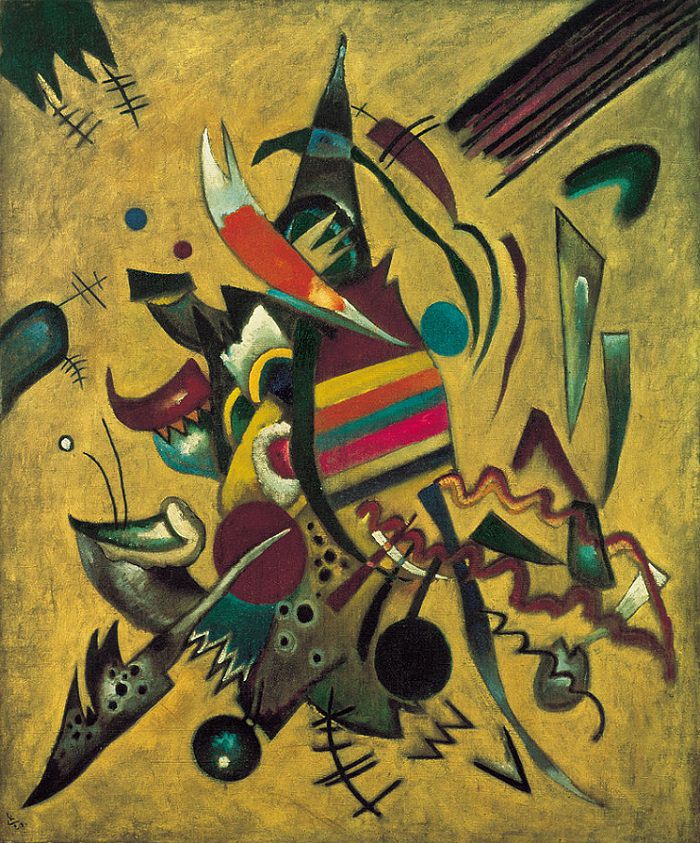
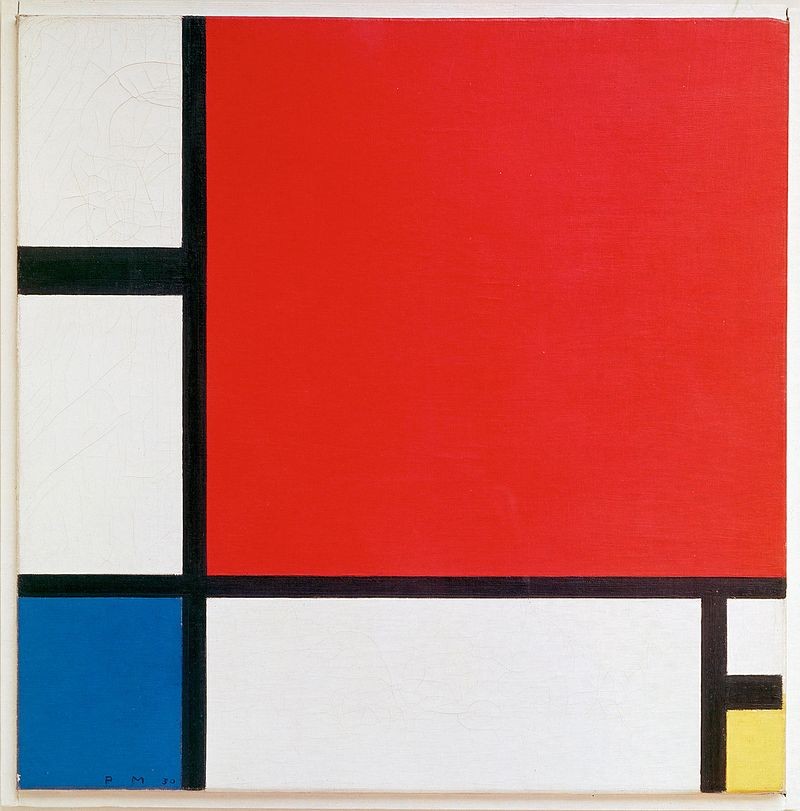


トレチャコフ美術館.jpg)