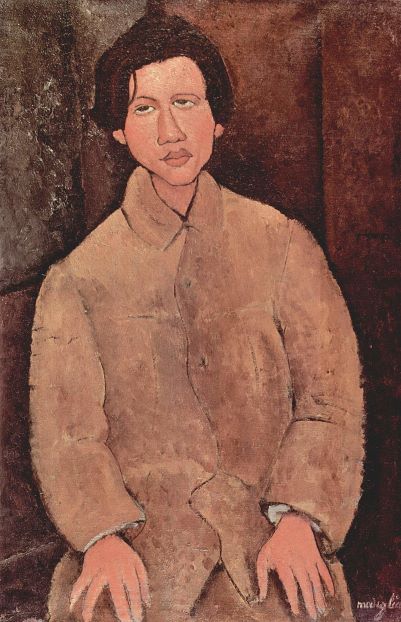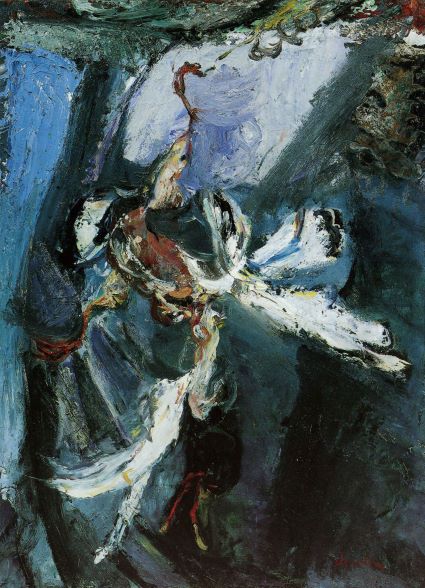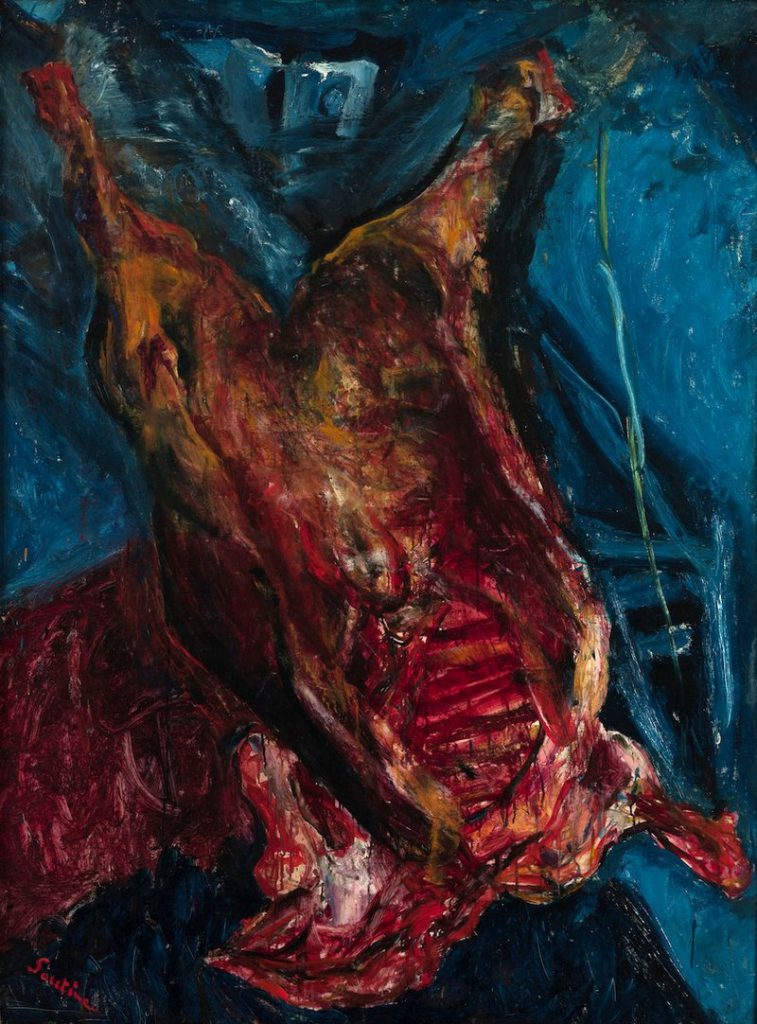ついにコクワガタがサナギになりました!

筆者はもはや、クワガタの成虫・幼虫・サナギの姿を見てもなんの抵抗もないのですが、そうではない方も多いと思います。前出の写真がちょっとピンボケなのは丁度いいかもしれませんね。そもそも入れ物が透明ではないですし。なんだかよく分からない状態のサナギ。筆者的にはもっとくっきりはっきり紹介したかったです。
一般的に、見たことがあるサナギと言えば、蝶のサナギでしょうか? 茶色でじっとしているイメージではありませんか? 筆者は蝶のサナギをじっくり観察したことがないので、そちらは詳しくないのですが、クワガタのサナギはブンブン動くんです! (再生ボタン▶を押すと動くサナギの13秒動画が見られます👇)
まだクワガタ飼育初心者だった頃、初めてこの動きを目撃して、かなり衝撃的だったことを覚えています。サナギが動いた?!みたいな感じです。サナギは、成虫になるのを動かずじっと待って羽化(うか:昆虫のサナギが成虫になること。)すると思っていましたので。 おしりの方を勢いよくブンブン動かします。その反動で全体が動くという感じです。この動画のサナギは仰向けの状態なのですが、この後少しして見てみるとうつ伏せになっていました。なかなかアグレッシブです。
サナギの期間は約3週間です。動くサナギも、羽化が近くなるとじっとしています。
他の幼虫たちは、見える限りではまだサナギになっていません。これから次々とサナギになっていくことでしょう。
ところで、お母さんコクワですが、無事越冬した後、亡くなりました。符節(ふせつ:昆虫の足の先のかぎづめ)もかなりとれていたので、寿命だったのかもしれません。飼育ケースに敷いたクヌギマットからちゃんと出て来て、昆虫ゼリーを少し食べて力尽きていました。世代交代ですね。
もうすぐ子どもコクワが成虫になった姿を見ることができます。楽しみです(^-^)