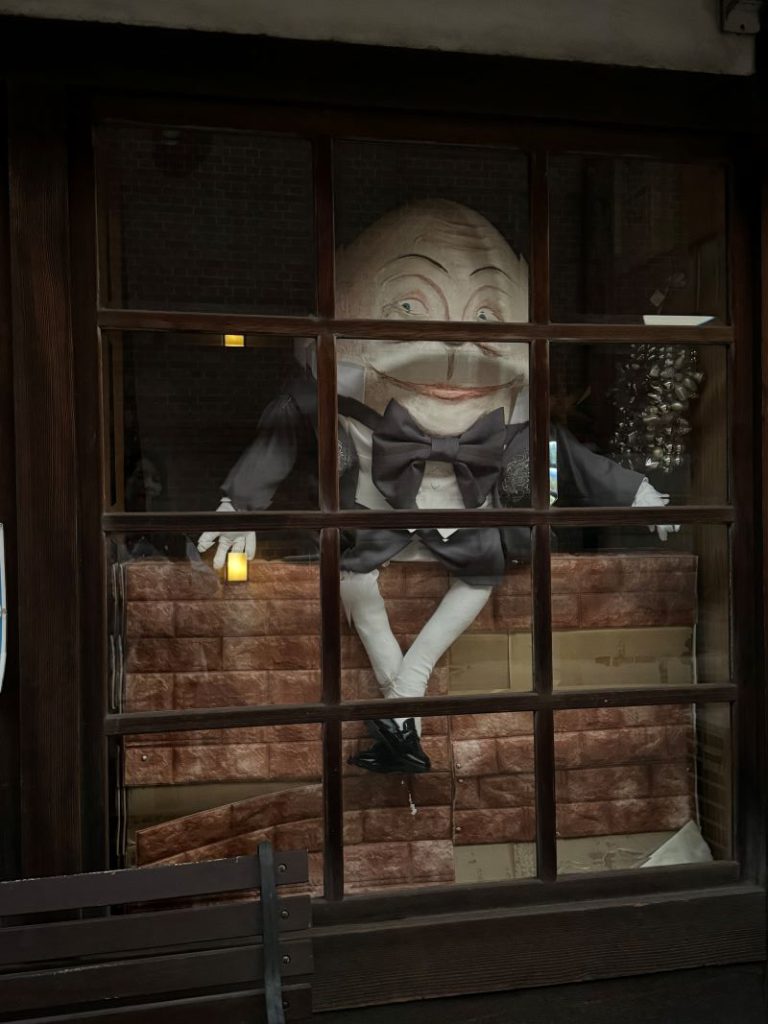倉敷アイビースクエアの床の柄はこんな感じです👇

赤と黒の市松模様(いちまつもよう:格子模様の一種で、二色の四角形を交互に配した模様)の床です。今まで特に問題意識もなく普通に歩いていましたが、気付いたんです。この柄は、超有名な画家の絵の中で見たことがあると。こちらです👇

ヨハネス・フェルメール(1632-1675)
『ぶどう酒のグラス』1661-1662頃
フェルメールの絵の中に描かれていました! フェルメールの作品は有名なものが多いのですが、よく見かけるのはこちらでしょうか?👇

ヨハネス・フェルメール
『真珠の耳飾りの少女』1665年?
市松模様は日本的な模様としてイメージされることが多いのではないかと思います。数年前に大ヒットしたマンガ(アニメ)『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎の上着のデザインが黒色と緑色の市松模様でしたね。2020年東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムにも市松模様をモチーフとしたデザインが採用されていました。
そんな市松模様、フェルメールは床の柄に多用しました。

ヨハネス・フェルメール
『二人の紳士と女(ワイングラスを持つ娘)』1660
白黒の市松模様の床もあります👇

(※イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館より盗難)
ヨハネス・フェルメール
『合奏』1664年頃

ヨハネス・フェルメール
『絵画芸術』1666年頃
(※『絵画の寓意』『画家のアトリエ』などど呼ばれる)
世界で愛される市松模様は、上下左右、無限に連結できることから、「未来永劫」「永遠」「繁栄」を意味する縁起の良い模様とされているようです。
また、市松模様をフェルメールは、
奥行きを出して鑑賞する人を描かれている部屋に引き込む効果を作るために用いた
ということのようです。
縁起の良い床の上を、フェルメールを思いながら歩くのもいいですね(^-^)