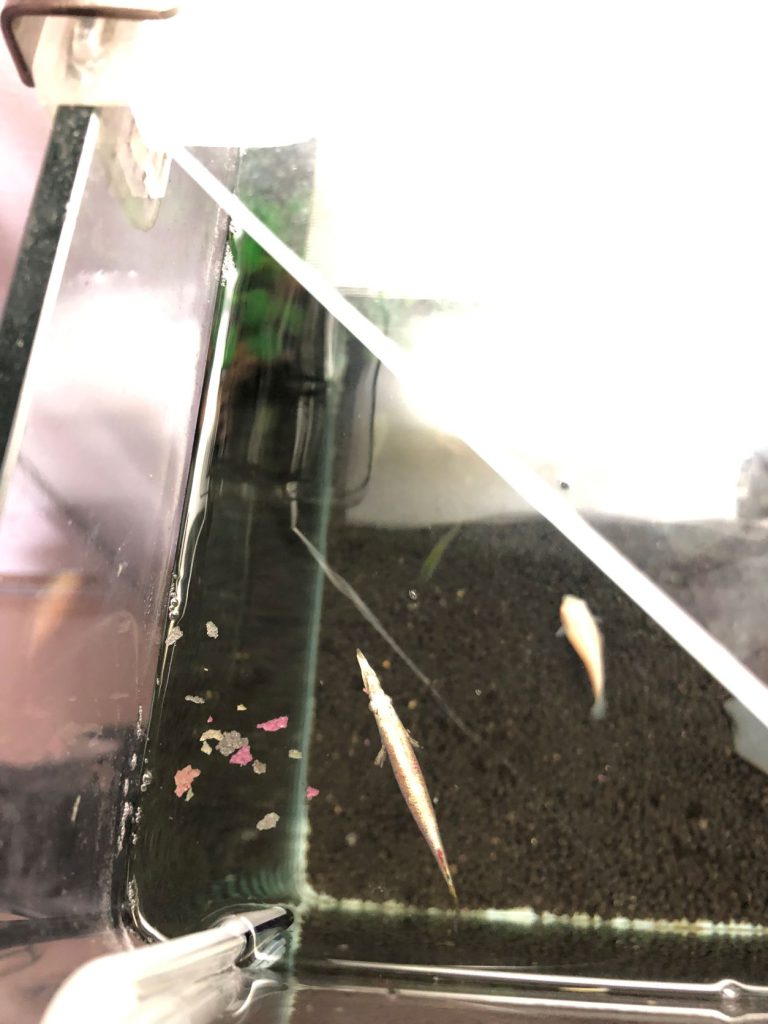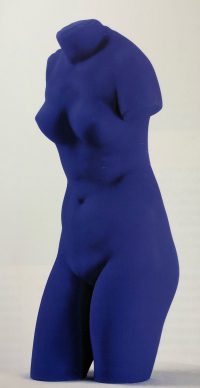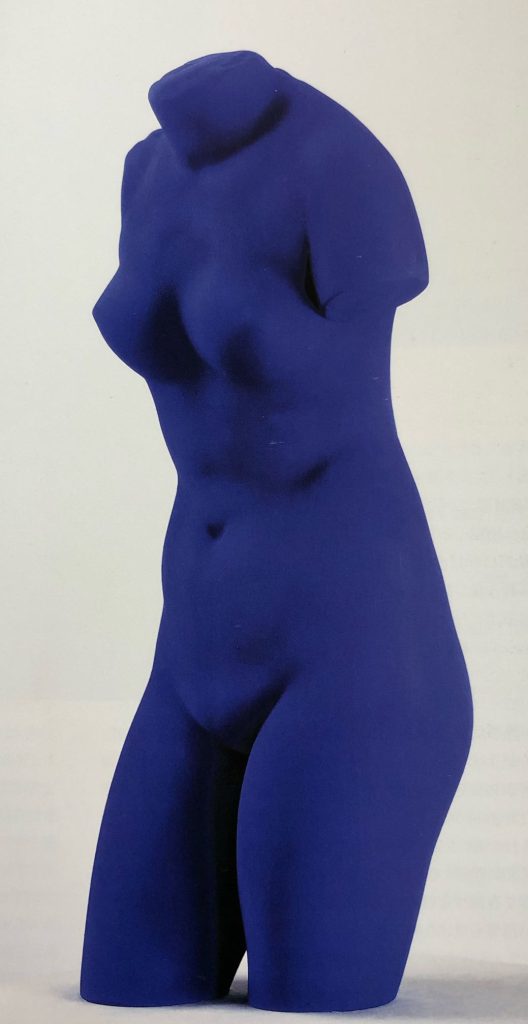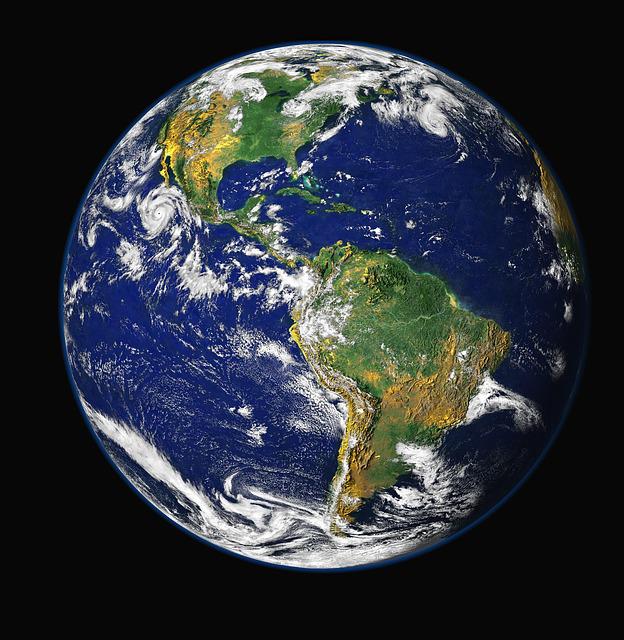3日前、アフリカン・ランプアイ(青い目のメダカのような魚)が1匹亡くなりました。このランプアイには、ちょっと思い入れがありました。というのも、一度水槽から飛び出た魚だったからです。朝起きて、水槽の横をふらふら歩いている時に見つけました。夜の間に飛び出たと思われ、かるく煮干し状態だったので、もう駄目だろうなと思いながらも、とりあえず水槽に戻してみました。数秒ぷかーっとしていましたが、なんとほどなく元気に泳ぎ始めたんです。ダメ元でしたが、水槽に戻してほんとに良かったと何度も思いました。そして2、3日はもつかなと思って観察していたら、なんと2カ月近く元気に過ごしてくれました。小さな魚の生命力の強さに人知れず感動した筆者です。
次に、サヨリのような魚ゴールデンデルモゲニーです。いつもは水面近くを泳いでいる魚です👇

2匹元気に泳いでいます。一回り大きくなりました。
そして、夜のゴールデンデルモゲニーがこちら。

誰にも見つからないぞと言わんばかりの場所をキープして休んでいます。こんなに底でも大丈夫なんですね。昼間とのギャップにちょっと驚きました。とにかく水面をスイスイ泳いでいる魚なので。魚(熱帯魚)の夜の様子は昼間と随分違うので、観察してみるとおもしろいですョ(^-^)
久しぶりに花が咲きそうです!


以前花を咲かせたアヌビアス・ナナ(過去記事、番外編:自宅水槽の水草)より葉っぱが大きいタイプのアヌビアス・バルテリーという水草です。ナナとよく似た感じの花を咲かせてくれると思います。
水質が安定していると花を咲かせるということのようなので、そういう意味でも、水草の蕾を発見するとヨシ👍という気分になります。